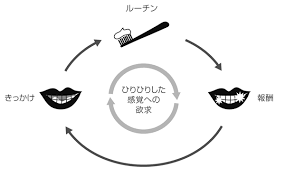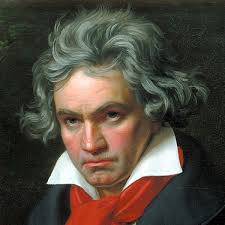私たちのアルバムのプロデューサーがグラミー賞受賞です!
“Visions Take Flight” はヒューストンでは「ROCO」の愛称で親しまれている River Oaks Chamber Orchestraのデビューアルバムです。 私は2014年以来ROCOのメンバーとして、鍵盤楽器を担当しています。このアルバムはROCOらしい。ROCOはモーツァルトやメンデルスゾーンなどのいわゆる定番クラシックも演奏しますが、何よりも沢山の委嘱作品の世界初演で有名です。このアルバムを制作するにあたって、創始者で総監督の首席オーボエ奏者、Alecia Lawyerが 団員に「今まで演奏した中で一番思い出に残る曲」とアンケートを取ったところ、5曲全てが委嘱作品!その5曲をそのままアルバムの演目にした、本当に民主的なROCOの風潮を反映したアルバムなのです。 英語ですが、アルバム制作中のヴィデオを下でご覧ください。 このアルバムのプロデューサーが「2020年のプロデューサー・オブ・ジ・イヤー、クラシック」カテゴリーのグラミー賞を勝ち取りました。私たちのプロデューサーはエネルギッシュで音楽に情熱的なBlanton Alspaugh。下のヴィデオでこのアルバムについて語っています。ヴィデオの後半で喋っているのはコンサートマスターのScott St. Johnです。 この受賞が格別嬉しいのは、録音の予定が一度無期延期になってしまったいきさつがあるかも知れません。元々このアルバムはテキサス州のラウンドトップにあるFestival Hill演奏会場で録音されるはずだったのです。予定日は2017年の9月。丁度、ハリケーンハーヴィーがヒューストン一体を洪水にしてしまったときの事です。 当初の録音予定日の前日。私の心の友にして、ROCOのクラリネット奏者である佐々木麻衣子さんはすでに洪水の心配のために、アパートの4階にある私の部屋に避難して来ていました。それでも私たちは、何とか運転して録音会場に行くつもりでいたのです。でもメールで録音の無期延期を知らされ、本当に気落ちしました。 その時の事情、そしてそれでも録音の日程を組みなおして「Harveyなんかに負けない!」と頑張ったROCOの奮闘記は下のヴィデオでご覧いただけます。 振り返ってみると、このアルバムがここまで深く音楽的に仕上がったのは、ハリケーンや無期延期を乗り越えて、録音に携わった全員が心を一つにして頑張ったからなのかも知れません。そして今回、そのプロデューサーがグラミー賞を受賞…本当に感無量です。この録音の一部となれたこと、ROCOの一員であること、そして人生のさまざまなチャレンジにも負けず、創造性豊かに生き続ける決意を曲げない人類の一員であることを、今日は特に祝いたいと思います。
私たちのアルバムのプロデューサーがグラミー賞受賞です! Read More »