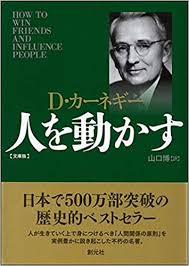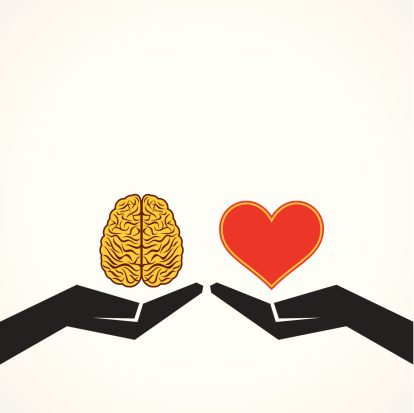書評:「人を動かす」(1936)
デール・カーネギー著「人を動かす」 「How to Win Friends and Influence People(1936)」 by Dale Carnegie 私はこの本を原文(英語)のオーディオブックで聞きました。 この本の存在は多分高校生くらいの時から何となく聞き知っていました。が、今読もうと思った理由はいくつかあります。 自分が「ハウツー本を書こう」と思い今その手の本を読み漁っている。 ニューヨーク公共図書館が創立125周年記念の一環として、創立以来一番貸し出しが多かった本トップ10を発表した際、この本が8位に入っていた。 2011年にタイム誌が発表した影響力のある本トップ100の19位に入っていた。 1936年に書かれたハウツー本が今でも影響力がある、と言うのは凄い。私はハウツー本と言うのは小説や哲学書に比べて普遍性が薄いと思っていました。それが今でも買われ続け、読み続けられているというのは、ちょっと空恐ろしい。 書かれている教訓と言うのは実に基本的な事です。「相手の立場を思いやる」「負けるが勝ち」「聞き上手になる」など万国共通の常識も、「常に笑顔」「相手の名前を連呼する」「どんなに小さな上達でも毎回手放しに誉める」などアメリカに特有な文化的なものもあります。このページで非常に読みやすい形に上手にまとめられています。 そしてこういう教訓を印象付けるために(教訓の一つは「論点を劇的に演出しろ」)ベンジャミン・フランクリンやリンカーンの武勇伝や外交手腕、さらに著者の受講生や友人、家族の逸話などが織り交ざります。 この本は私にとっては好ましいものではありませんでした。「胸糞が悪い」と言ってしまっても良いかも知れません。要するに、どうやって人に対応すれば最終的に自分の目的を達成できるか、と言う本だからです。 しかし、これも最近始めたことなのですが、読書後にその本の背景に関する情報や他の方の書評を読むことで、また新たな視点を得ることが出来ました。 この本は1929年の世界大恐慌の7年後に出版されています。不景気の余波で、この年のアメリカの失業率は16.9%。この本に「危うく首になるところだったがこのテクニックを使ってボスに気に入られた」とか、「このテクニックを使った何々さんは売上高が急上昇した」と言う逸話が多いのは、要するに出版当初の読者は背水の陣でこの本で学んだ教訓を実践していたのです。更にこの本がそういう不景気の中で爆発的に売れた理由、そして今でも売れている理由は、この本が時勢問題に全く触れず、「どんな状況下でもすべては自分次第」と言う視点から論点を展開し続ける、と言う点です。自分が変われば周りも変わる。自分が努力をすれば自分の人生は変わる、と言う論点です。それは他の方の書評を読んで、初めて気が付きました。 ただ懸念されるのは、その後もこの本が読まれ続けたことです。16の時からの私のホームステー先で、今では私の「アメリカの両親」の老夫婦はお父さんが1924年生まれ、お母さんが1935年生まれでした。この二人がこの本を読んだことが在るかどうかは知りませんが、この二人の人への接し方には、明らかにこの本の影響が感じられます。要するにこの本はアメリカの社交文化に多大なる影響を与えていると言って過言ではないと思います。そしてそれが、アメリカ人の愛想よさ、不必要なまでの友好性、表面的な会話などの根源にあるのでは、と思います。 この本はアメリカ文化背景や、アメリカ特有の会話術などを学ぶためには、非常に有効な本だと思います。が、個人的には、次に書評を書く「7つの習慣」の方がより好ましく、素直に読め、学ぶポイントも多かったです。