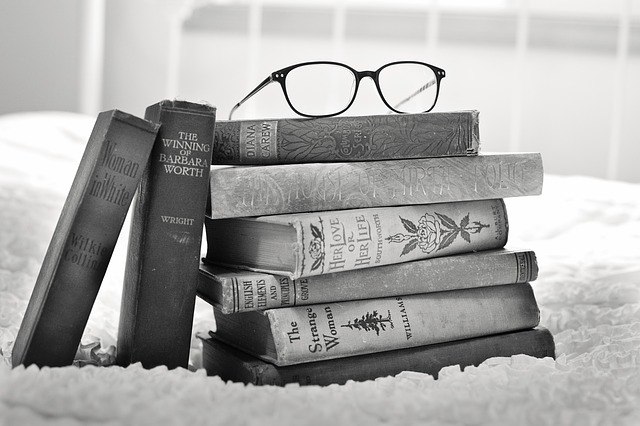書評:恩田陸「蜜蜂と遠雷」をピアニストとして読むと…
日本に帰って来る度の楽しみには色々(食!)あるが、乱読もその一つである。平田家はみんな本が好きなので、帰ってくるとすでに両親からの「推薦読書」が結構ある。妹が漫画をシリーズで図書館から借りておいてくれてある時もある。今年は特にUS-Japan リーダーシップ・プログラムへの参加を来月に控えて、みんなの推薦読書がより硬派になっている。私の音楽馬鹿さ加減を一か月で解消しよう、と言う野望には無理があるが、でも面白く・ありがたく読み進んでいる。 今日のブログには今年の直木賞受賞で話題になった、国際ピアノコンクールを描いた小説「蜜蜂と遠雷」について書きます。この本は私の演奏会に来たお客様にも意見を求められるほどだった。今朝読破。小説の中心になる4人の登場人物がコンクールに勝ち残れるのかどうか、気になってぐいぐい読んでしまう。まず第一印象から言うと、この小説はバレーを題材にした少女漫画(例えば有吉京子の「スワン」)によく似ているな~、と思った。そしてピアニストとしてピアノ・レパートリーの描写をどう思うかと聞かれると、私は筋を追う事に専念して、特に小説の終わりの方はそう言う所は読み飛ばしている自分を発見した。一般のお客さんには「ピアニストは演奏中何を考えているのか」と言う興味に夢が出て、この小説のお陰でクラシックの人気が高まるのかも知れない。そうすれば私もうれしい。今回の帰国で、家族の気遣いが例年より細やかなのも、もしかしたらこの小説のお陰なのかもしれない。私がこの小説で一番共感したのは、「練習と言うのは掃除に似ている」と言う所である。曲(家)が小さければ、掃除も簡単。でも曲(家)が大きくて、構造が複雑であればあるほど、その家をきれいな状態に保っておくことが難しくなってくる。一か所をきれいに保つことを集中すると、他がいつの間にか汚くなっている。でも、段々効率よくその家をきれいにすることをマスターするとやがて、花を飾ったり、特別にぴかぴかに磨いたりして、自分らしさを演出することが出来るようになる。この描写は(そう言う云い方もできる!)と深く共感した。それから本番前と演奏中の緊張の描写。特に三次予選トップバッターがプレッシャー負けして暴走する部分は、凄い洞察力・描写力だと思った。恩田陸は幼少からピアノを習い、大学時代にはビッグバンドでのサックス演奏経験などもあるようだが、それにしてもすごい。 でもやっぱり、少なくともピアニストとしての私の実感とは違うな~と言う所もある。そして風間塵と言うキャラクターはかなり現実離れした状況設定。曲に対する奏者の事細かなイメージ描写も、う~ん、やっぱり音楽とか音楽体験を言語化することの限界を感じてしまう。それから小説に於いて注目されるコンテスタントの二人が日本人、もう二人が日本人とのハーフと言うのも、この小説は国際的にはベストセラーにならないな、と私が思う理由である。あと、もう少し違う国の教育とか音楽観とかピアノ技術へのアプローチの違いを浮き彫りにした方が、舞台を国際コンクールにした理由がもっと生きるな、と思った。 同じく音楽を題材にこれから色々執筆しようと思っている私が一番うれしかったのが、ナクソス・ジャパンとの提携で小説で出てくる曲全てを、著者のイメージと合った演奏で聴ける、と言うサービスがあること。http://www.gentosha.jp/articles/-/7081 私も自分の著書にはCDを付録して出版したいと思っている。私の場合は自著自演になるけれど。
書評:恩田陸「蜜蜂と遠雷」をピアニストとして読むと… Read More »